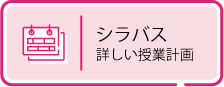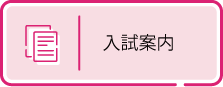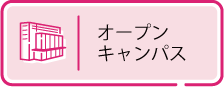About Us
Special Study
社会生活情報学専攻
Major in Social Science and Information Studies
情報社会を広く深く理解し、
自分自身をしっかり表現する
力を身につけていきます
環境情報学専攻
Major in Environment and Information Studies
住まいやまちづくり、自然や社会のしくみなどを通して
環境と共生する持続可能で快適なくらしを考えます。
情報デザイン専攻
Major in Information Design
情報科学、認知科学、デザインなどから
人と情報について深く理解し、伝わる情報を創ります。
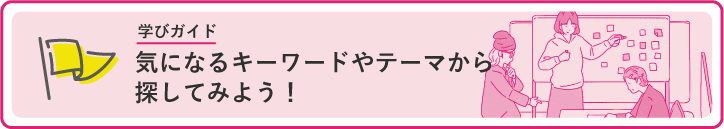
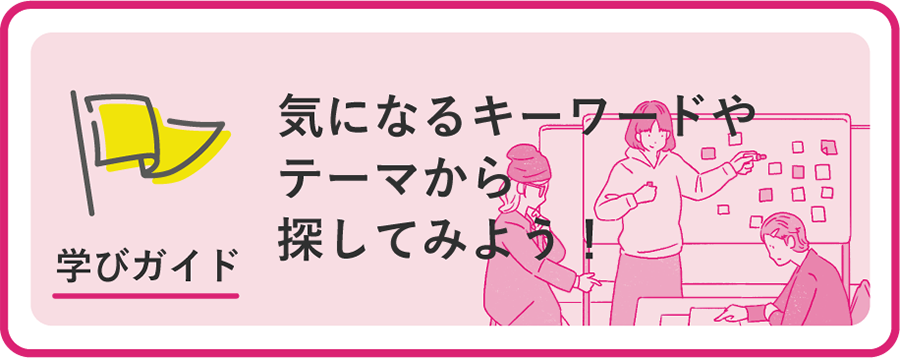
Voice of Graduate
就職・資格のこと。卒業生の声より
2020年/社会生活情報学専攻 卒業
株式会社横浜銀行
神本夕奈さん
神奈川県立希望ケ丘高等学校 出身

専攻で学んだ経済の知識を生かして金融の総合コンサルティングを行っています
Q.現在の仕事内容を教えてください。
個人のお客さまに対して、資産運用・相続対策・不動産活用など、金融の総合コンサルティングを行っています。税理士や不動産会社とも提携しながら、お客さまの人生設計に寄り添った提案を心掛けています。
Q.仕事のやりがいを教えてください。
金融商品には形がないため、営業担当者の人間力が問われます。お客さまから「あなたに相談してよかった」という言葉をいただけると大きなやりがいを感じます。
Q.大学での学びはどのように生かされていますか。
経済学の授業で修得した知識のすべてが現在の仕事に生きています。また学生時代から新聞を読む習慣を身につけてきたことも役立っています。新聞を読むことで経済動向をつかめるだけでなく、お客さまとの何気ない会話にも活用できます。またそこから金融に関するニーズを見つけ、新たな提案につながることもあります。
Q.今後の目標や抱負を教えてください。
金融はもちろん、税務、不動産、法律など、幅広い分野で業務に必要な知識をアップデートしていかなければなりません。そのため毎日が勉強の日々です。お客さまからいつでも頼られる存在になれるよう、今後も知識を深めて成長していきたいです。
2020年/社会生活情報学専攻 卒業
株式会社三菱UFJ銀行
鈴木詩栞さん
神奈川県立茅ケ崎高等学校 出身

専攻で身につけた金融の知識があるから責任感を持って業務に取り組めます
社会生活情報学専攻にはWord、Excelなどオフィス系ソフトを使用する授業が多数あります。 私はパソコン操作が苦手だったのですが、社会に出たら必須のスキルだと思い、あえてオフィス系ソフトを使う科目を重点的に履修しました。課外パソコン講習も受講し、2年次にはMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)に合格。就職した現在も毎日使うツールなので、在学中に苦手意識を克服できてよかったと実感しています。
就職活動では、専攻で学んだ金融知識を生かしたいと考え、株式会社三菱UFJ銀行に入社を決めました。専攻で金融の歴史や役割を学ぶなかで、金融機関が経済に大きな影響を与えうることを理解できたため、強い責任感を持って働いています。これからも学び続ける気持ちを忘れず、お客さまと社会に貢献できる人材を目指していきます。
2019年/社会生活情報学専攻 卒業
コナミビジネスエキスパート株式会社
川井愛理さん
千葉県立松戸六実高等学校 出身

相手の立場で考え、伝える力を大切に、心のこもったお客さま対応に努めています
ゼミでは多様な分野を学んだ上で卒業研究のテーマを決めることができ、私は「アイドル」をテーマに取り組みました。アイドルファンの行動と宗教信仰の類似性に着目した研究を進めるうちにエンターテインメント業界への興味が強くなり、コナミビジネスエキスパートへの入社のきっかけにもなりました。
現在は、総合受付でお客様の接遇業務を担当しています。受付は会社のイメージにつながる重要な役目です。相手の立場で物事を考え、分かりやすい説明をすることの重要性など、大学で実践的に習得したコミュニケーションスキルが日頃のお客さま対応に生かされています。海外からのお客様をアテンドする機会も多く、ネイティブの先生の授業で鍛えられた英語力が大いに役立っていると実感します。今後もさらにスキルを磨き、会社のイメージアップに貢献できるよう努めてまいります。
2014年/社会生活情報学専攻 卒業
デサントジャパン株式会社
木村奈穂さん
東京都私立トキワ松学園高等学校 出身

ラクロスウェアの開発が夢です
興味があった経済学に加え、幅広く学べる社会生活情報学専攻に魅力を感じ、進学しました。また高校時代所属していたラクロス部の練習試合で大妻女子大学を訪れた際に、グランドが広く、整った練習環境に憧れを持ったのも決め手のひとつでした。希望通りの就職がかなったのは、在学中に努力した勉強とラクロス部の練習、そしてゼミの先生のお力添えや、就職支援センターによる筆記試験・面接対策の講座など充実したプログラムのおかげだと感謝しています。
私が携わる営業事務は、正確でスピーディーな事務処理能力が不可欠で、授業でパソコン技術を基礎から習得できたことが大きく役立っています。自分が手配した商品が店舗に並ぶのを目にするのが毎日の喜び。デサントでまだ取り扱いのないラクロスウェアを開発するのが私の夢です。
2019年/環境情報学専攻 卒業
大和ハウス工業株式会社
夏目梨帆さん
神奈川県立上溝南高等学校 出身

目標としていた二級建築士の試験に合格。さらに、一級建築士を目指して学び続けます
環境情報学専攻を志望したのは、身近な住宅を中心とした建築が学べて、卒業と同時に二級建築士の受験資格を得られることに魅力を感じたからです。在学中は、住居・建築・環境に関わる分野について新しい知識を吸収できることが楽しく、4年次には自分も学びながら後輩にも教えるSA*の活動も経験しました。
就職活動では、企業研究を進めるうちに大和ハウス工業の幅広い事業展開と社風に惹かれ、入社を決めました。現在はさまざまな建築現場を回って研修を受けています。ホテルや店舗などの商業施設の工事を一から学び、使用される重機や材料、建物の構造などについて幅広く学んでいるところです。入社1年目で二級建築士の試験に合格。次は一級建築士を目指し、さらなる勉強も始めています。
*スチューデントアシスタントの略。在学生による実験や演習などの教育補助のこと
2016年/環境情報学専攻 卒業
伊藤ハム株式会社
田中沙樹さん
東京都私立杉並学院高等学校 出身

伝えたい、「食」の大切さ
大学では、食にも大きく関わる分野である環境サイエンスを中心に学びました。特に力を入れた「カリウムの土壌推移」についての研究では、一度で成功しない実験に何度も根気強く取り組み、プレゼンテーションを繰り返しました。それらの取り組みが、社会人としての姿勢や振る舞いなどの土台を築くことにもつながり、仕事をする上でとても役立っています。
就職先に食品業界を志望したのは、コミュニケーションを生み、家族の絆を深める食事の大切さを子どものころから感じていたためです。現在は営業職としてハムやウインナーなどのパンに入れる業務用商材を取引先にご提案しています。女性ならではの視点が求められる場面も多く、積極的に活動したいと思います。
2014年/環境情報学専攻 卒業
ミサワホーム株式会社
鎌田奈緒さん
茨城県立日立第一高等学校 出身

インテリアの知識が仕事に役立っています
住環境やインテリアに関することを文系・理系にかかわらず学べることに魅力を感じ、環境情報学専攻を志望しました。中でも、設計の授業は印象深く、手書きの図面を作成しながら、理想の住宅を考えていくことにやりがいを感じていました。さまざまな専門知識や物を見る目を養い、インテリアコーディネーターの資格取得をめざそうと勉強を始めたのもそのころです。希望していた住宅メーカーに就職が決まり、その後無事、資格試験に合格。現在では、設計業務のフォローを担当しています。
取得した資格や知識を仕事でしっかりと生かして、インテリアコーディネーターとして活躍することが目標です。これも、在学時にゼミで特別講座を開いてもらうなど、インテリアのあらゆることを教えていただいたおかげと感謝しています。
2014年/環境情報学専攻 卒業
横浜市立横浜総合高等学校 教諭
能登愛さん
神奈川県私立桐光学園高等学校 出身

地球環境への理解を深める授業を心がけて
環境情報学専攻を志望したのは、幼少期から関心があった南極や地球環境について学びつつ、理科の教員免許状を取得するためでした。横浜市の高校で理科教員になる夢を叶え、現在は1年生の担任です。生徒たちが日々成長していく姿は何よりの喜びで、子ども一人ひとりに向き合い、学校生活や卒業後の進路に関して共に考え、心に寄り添った指導を行うよう心がけています。
在学中に学んだCT(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)や、「理科」に加えて「情報」の教職課程を履修したことで、生徒にわかりやすい授業づくりに役立っています。今後は、地球環境に対する理解をより深めてもらうためにも、「教員南極派遣プログラム」に挑戦し、現地から生中継での「南極授業」を実現させることが私の目標です。
2016年/情報デザイン専攻 卒業
住友電工情報システム株式会社
岩永秀美さん
東京工業大学附属科学技術高等学校 出身

勉学と部活動に打ち込んだ4年間。社会人として大切な考え方を学びました
大学時代は、勉学と舞踏研究部の活動に打ち込み、忙しくも充実した4年間を過ごしました。その中で学んだことが社会人になってから生かされる場面が多々あります。情報分野の基礎知識はもちろんですが、研究を進める中で身につけた目標を達成するための進行管理能力や、先生からいただいた「相手にとってどんな価値を提供できるかをアピールすべき」というアドバイス、また部活動で培ったチームワークの大切さなど、どれも社会で働く上で非常に大切なことだと痛感しています。
現在はシステムエンジニアとして、国内工場で利用されるシステムの開発・保守を手がけています。ゆくゆくは、お客様の業務を改善するためのよりよいシステムを、自ら提案・提供できるようなエンジニアになりたいです。
2019年/情報デザイン専攻 卒業
日本ヒューレット・パッカード合同会社
伊駒佳純さん
東京大学教育学部附属中等教育学校 出身

大学で学んだプログラミング言語の知識がSEとしての業務にもつながっています
大学入学前から将来はシステムエンジニア(SE)になりたいと考えていたため、設備や学びの内容が魅力的で、専攻分野以外の資格取得にも力を入れられる大妻の情報デザイン専攻を選びました。在学中は、ITパスポート試験、図書館司書の資格を取得するなど勉学に励みました。卒業研究では、私が最も得意としたJavaScriptを使ったWebアプリケーション開発に力を入れて取り組みました。
卒業してから気付きましたが、大学でJavaScript、C言語、Java、PHP、SQL、Pythonなど複数のプログラミング言語を学べたことは、ほかではなかなかできない貴重な経験でした。SEになった今、どの言語が何を作るのに向いているのかをすぐに理解できるのも専攻で修得した専門知識があるからだと思います。
就職活動では、幅広い業界にシステムを提供して社会を動かしていくSIer(エスアイアー※)のSEを志望。現在は、通信業界に特化した部署のSEとしてプロジェクトに関わっています。任されている部分も大きく仕事にやりがいを感じています。今後は、目標であるプロジェクトマネージャーに関わる資格の勉強を続けながら、実務経験を積みステップアップしていきたいと思います。
※システムを構築する企業のこと
2020年/情報デザイン専攻 卒業
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)
原田莉子さん
東京都私立大妻中野高等学校 出身

ペーパーレス化から獣害対策までICTを駆使して課題を解決
Q.現在の仕事内容を教えてください。
システムエンジニアとして、自治体が抱える多様な課題を、ICTを用いて解決しています。ペーパーレス化やネットワーク環境に関する提案・工事・サポートのほか、鳥獣による被害から農作物を守るためセンサーを利用して効率的に罠わなを仕掛けるなど、一次産業を支援することもあります。
Q.仕事のやりがいを教えてください。
お客さまのお困りごとをヒアリングし、お客さまにも見えていない潜在的な課題を見つけ、相手の立場に寄り添って解決へと導くことができたときにやりがいを感じます。
Q.大妻での学びはどのように生かされていますか。
プログラミングの知識が業務に直結しているのはもちろんですが、色使いなどデザインに関する学びも、提案資料を作成する際に大変役立っています。また、先生方に親身になってご指導いただいた経験から、分からないことは素直に聞き、学びを深める姿勢が大切だと気付きました。
Q.今後の目標や抱負を教えてください。
ネットワークや情報通信技術の知識をさらに蓄積したいです。確かな知識と技術を持ち、お客さまの悩みに対して適切な提案ができるシステムエンジニアを目指しています。
2020年/情報デザイン専攻 卒業
本田技研工業株式会社
高松朋美さん
東京都私立郁文館高等学校 出身

専攻の課題制作で培った粘り強さを武器に開発設備の調達を担っています
Q.現在の仕事内容を教えてください。
研究開発設備の発注業務を担当しています。全長10メートルを超える大型設備を発注することもあり、スケールの大きさに気を引き締めながら業務に取り組んでいます。
Q.仕事のやりがいを教えてください。
より性能のよい設備を、より早く、より低価格で調達することが求められる仕事です。交渉に苦労することもありますが、無事に調達できたときは会社に貢献できたという大きなやりがいを感じます。
Q.大学での学びはどのように生かされていますか。
理想の形になるまで諦めずに取り組んだプログラミングの課題制作の経験から粘り強さを、また、スポーツフェスティバルに実行委員長として参加した経験からコミュニケーション能力を習得しました。それらの力が、関係部署との連携や調整、取引先との交渉の際に大いに生かされています。業務改善のためにパソコンを使ってできることは何でもやってみるという姿勢は、専攻で身につけたものです。
Q.今後の目標や抱負を教えてください。
査定や交渉など、設備の調達業務に必要な知識をさらに身につけたいと考えています。将来的には、設備がどのように使われているかを知るために開発現場での業務も経験し、そこで得た知見を再び調達に生かしたいです。







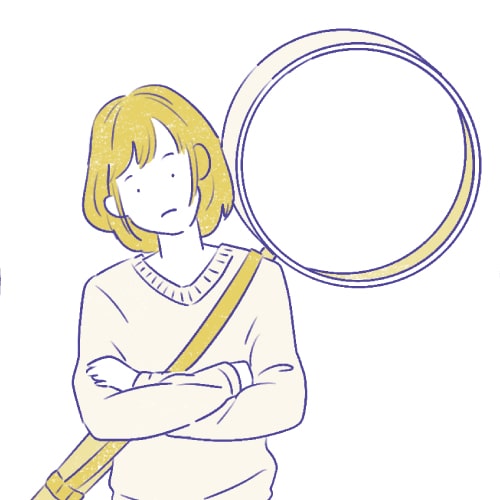
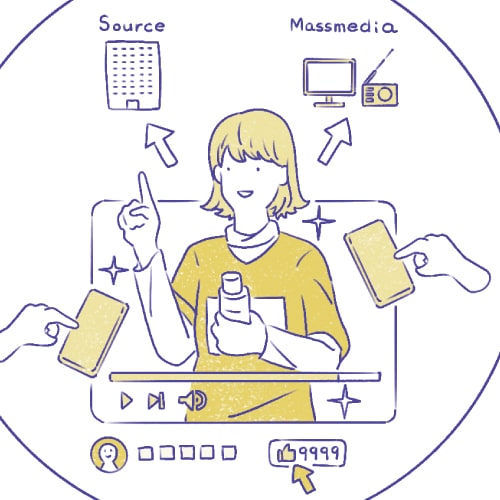
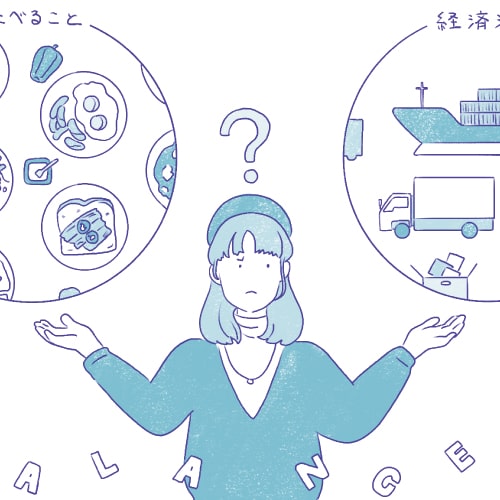
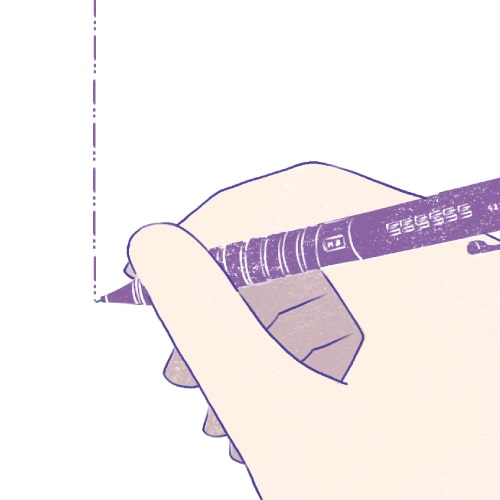
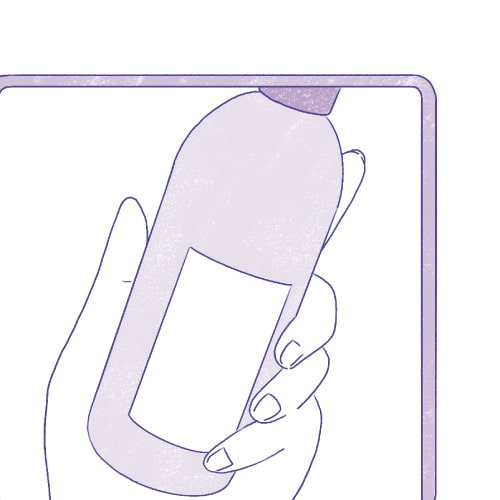

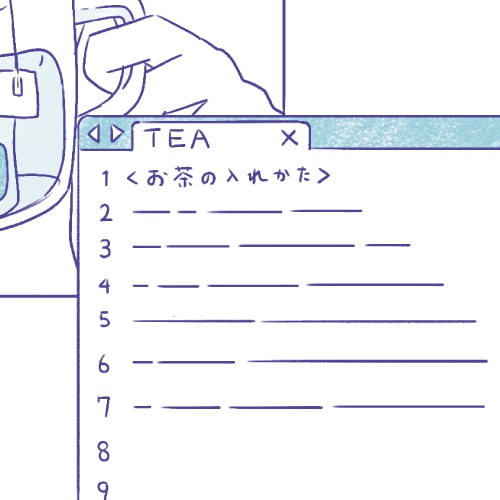
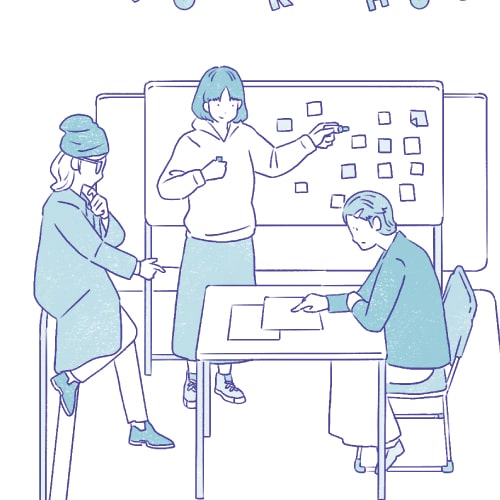












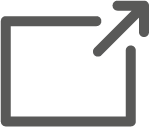 大学総合案内
大学総合案内 社会生活情報学専攻パンフレット
社会生活情報学専攻パンフレット 環境情報学専攻パンフレット
環境情報学専攻パンフレット 情報デザイン専攻パンフレット
情報デザイン専攻パンフレット